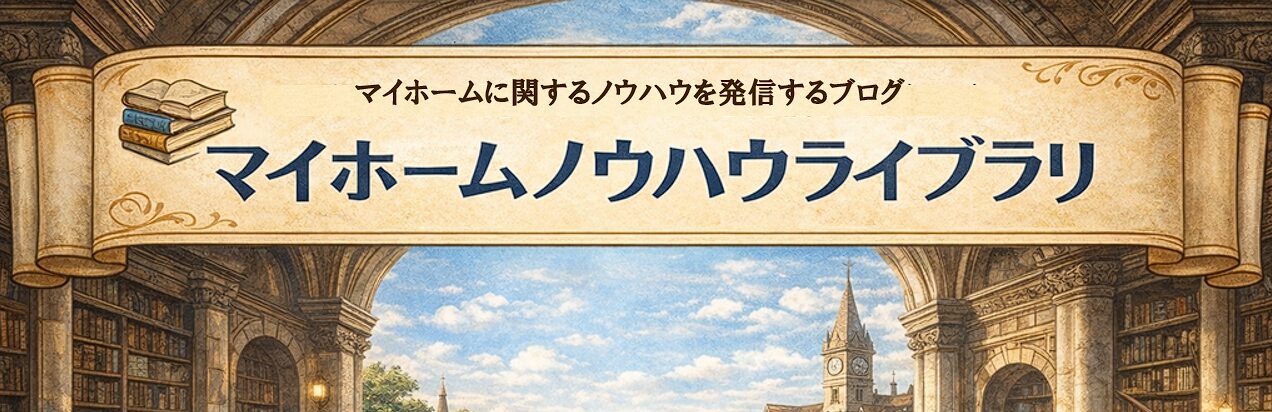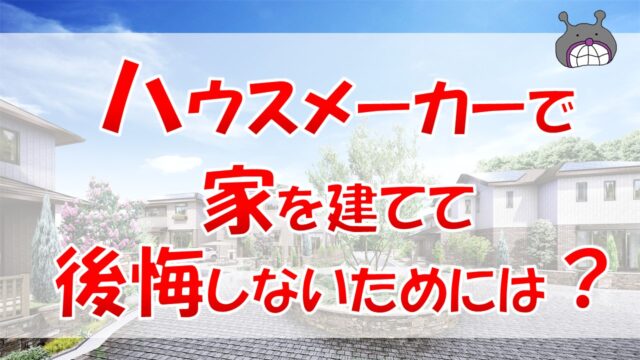「災害に強い家を建てる3つのポイント」
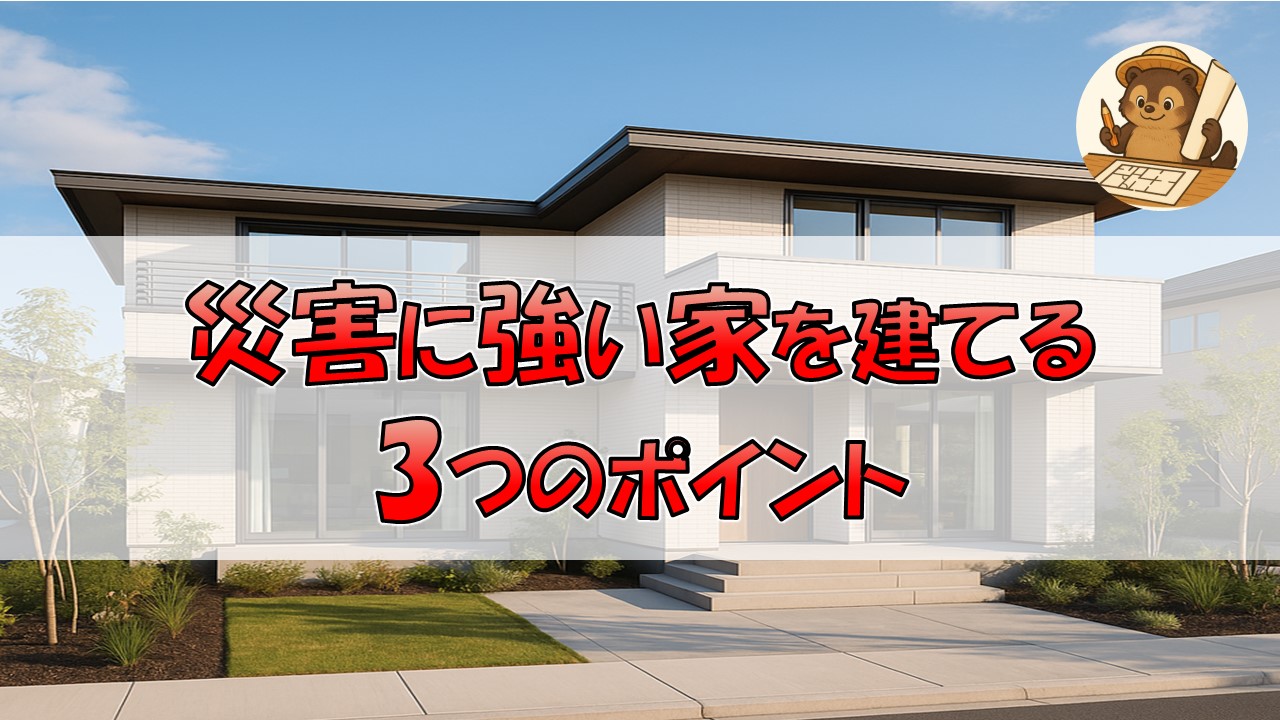
こんにちは。ぴーぴーまんです。
今回は「災害に強い家を建てる3つのポイント」というテーマでお話ししていきます。
2024年8月8日、政府から初めて「南海トラフ地震 臨時情報」が発表されました。
幸いなことに、これまで大きな地震は起きていませんが、あらためて「大地震リスクは現実のもの」だと感じさせられました。
そして、地震だけでなく、台風・大雨・洪水・土砂災害・津波・大雪・火山噴火などなど…。
私たちが暮らす日本では、災害のニュースを聞かない年なんてほとんどありません。
本当に「災害大国ニッポン」だと実感しますよね。
これだけ多くの災害が発生しているからこそ、
「どうすれば災害に強い家を建てられるか?」は、これから家を建てる人にとって避けて通れない大切なテーマです。
今回は、災害に強い家を建てるためのポイントを、私なりの視点でまとめました。
ぜひ最後まで読んで、家づくりのヒントにしてもらえたら嬉しいです😊
それでは、さっそく始めていきましょう!
災害に強い家を建てるには
いきなりですが、結論からお伝えします。
災害に強い家を建てるためには、この3ステップが大切です👇
1️⃣ 被災する確率の低い場所を選ぶ
2️⃣ 被害が起きにくい家を建てる
3️⃣ 災害時に困らない家にする
それぞれ、順番に解説していきます!
~この記事の内容~
① 被災する確率の低い場所を選ぶ
まず大前提として、災害が起こりにくい場所に住むのが、いちばん確実な防災対策です。
例えば高台に住めば、大雨による水害リスクはグッと減りますよね。これは過去の災害の歴史がしっかり証明しています。
ハザードマップを活用しよう
災害の「いつ起きるか」はわかりませんが、リスクの大きさや種類はある程度予測ができます。 そこで頼りになるのが各自治体が作成している「ハザードマップ」です。
👉 国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、全国どこの地域でも地図上で簡単にリスクが確認できます。
家を建てる前に、必ずチェックしてその土地のリスクを事前に把握しておきましょう!
 ※ハザードマップの一例。画像はハザードマップポータルサイトより引用
※ハザードマップの一例。画像はハザードマップポータルサイトより引用
地盤の強さも要チェック
もう一つ見逃せないのが地盤の強さです。いくら丈夫な家を建てても、地盤が弱ければ地震には勝てません。
特に海や川の近くは要注意。さらに、昔は川や池だった場所(いわゆる「軟弱地盤」)も油断できません。
おすすめは「住まいの安心研究所」など、地盤調査の結果や昔の航空写真が見られるサイトを使うこと。これで、その土地の成り立ちや地盤の強さを事前にチェックできますよ👌
② 被害が起きにくい家を建てる
次のステップは、「万が一災害が起きたときに備える家づくり」です。
災害自体は防ぎようがありませんが、被害を最小限に抑えることはできます。ここでは、そのために大切なポイントをご紹介していきます😊
地盤をしっかり強化しよう
たとえ立地があまり良くなくても、家の仕様でリスクを軽減することが大切です。
まずは基本中の基本、地盤の強化。
地盤が柔らかいと、地震の揺れが大きくなり、建物の倒壊リスクが高まります。
👉 地盤改良工事は、地盤の状態によっていくつか種類があるので、事前に専門家に地盤調査を依頼し、最適な工法を選びましょう。
水害には「土地の高さ」で対策
水害リスクがあるエリアでは、盛り土などで土地の高さを上げるのが有効です。
先ほど紹介したハザードマップを見れば、洪水時の浸水深さも確認できるので、「どのくらい盛れば安心か」が具体的にわかります👌
耐震性はとても重要
建物自体の耐震性も見逃せません。
耐震性は「耐震等級」という指標で評価されますが、私としては「耐震等級3」が必須レベルだと考えています。
これなら、大地震後も安心して住み続けられます。
工法と間取りにも注目
工法は主に👇
- 木造
- 鉄骨造
- RC造(鉄筋コンクリート造)
とありますが、一般的にはRC造 > 鉄骨造 > 木造の順で耐震性が高いとされています。ただし、どの工法でも設計&施工がしっかりしていれば十分な耐震性が確保できるので、信頼できる業者選びがカギです。
間取りの工夫も重要です👇
- 柱を増やす
- 窓を減らして耐力壁を増やす
- 四角・長方形などシンプルな形にする
反対に、大きな窓や吹き抜けは耐震性の面では少し不利なので、デザインと安全性のバランスをよく考えることが大事です。
家具の転倒対策も忘れずに
意外かもしれませんが、地震のケガの多くは家具の転倒が原因です。特に重症になりがちなのが、食器棚やタンスの下敷き。
- 家具をしっかり固定する
- 大型家具が不要なように収納をたっぷり確保する間取りにする
などの工夫も大切です!
さらに安心感をプラスするなら
- 免震装置・制振装置で揺れそのものを抑える
- 割れにくい窓ガラス
- 耐風性の高い屋根・外壁
- シャッターの設置
などもおすすめです。費用はかかりますが、安心感はぐっと高まりますよ✨
- 以上のように、家の仕様を工夫することで、災害時の被害をできる限り抑えることができます。
 ※地中改良工事の一例
※地中改良工事の一例
③ 災害時に困らない家にする
最後のステップは、「もしものときに困らない家をつくる」ことです。
大きな災害が起きると、停電や断水などライフラインが途絶えるリスクが一気に高まります。
短時間ならまだしも、長期間の停電・断水となると、命にも関わる重大な問題ですよね。
特に台風被害の多い地域や、高齢者・小さなお子さんがいるご家庭では、その影響はさらに大きくなります。
だからこそ、事前の備えがとても重要なんです💡
「貯める」設備で備える
こうした事態に役立つのが👇
家庭用の貯水タンク
蓄電池
などの「貯める設備」です。
さらに、蓄電池だけでなく太陽光発電システムがあれば、日中は発電して電気を補充できるので、より長期間の停電にも対応できます🌞⚡
エコキュートも“非常用タンク”に!
少し余談ですが、オール電化住宅で使われることが多いエコキュート。
実はこの設備、構造上タンクにたくさん水が入っているので、非常時には生活用水として活用できるんです🚿
クルマも非常電源に!
最近の電気自動車や一部のハイブリッドカーでは、非常時にクルマから家に電気を供給できる機能を備えている場合があります。
普段の生活で使っているものがいざというときの備えにもなるって、とても心強いですよね😊
コスパ重視なら…
エコキュートや電気自動車のように、「日常的に使える+非常時にも役立つ」設備は、費用対効果の面でも賢い選択です。
新築時に取り入れるなら、ぜひこうした視点も加えてみるといいと思います✨
まとめ|災害に強い家づくりのポイント
いかがでしたでしょうか?😊
今回は「災害に強い家を建てるには?」というテーマで、
1️⃣ 被災する確率の低い場所を選ぶ
2️⃣ 被害が起きにくい家を建てる
3️⃣ 災害時に困らない家にする
…という3つのステップを詳しくご紹介しました。
簡単にまとめると👇
できるだけリスクの少ない土地を選ぶ
耐震性・耐水性の高い家を建てる
蓄電池・貯水設備などでライフライン対策を整える
これらを意識することで、災害後も安心して暮らしを維持できる家づくりが可能になります✨
今回の記事が、皆さんの家づくりのヒントになれば嬉しいです。
ほかにもお役立ち記事を用意していますので、ぜひ他の記事もチェックしてみてくださいね😊
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!